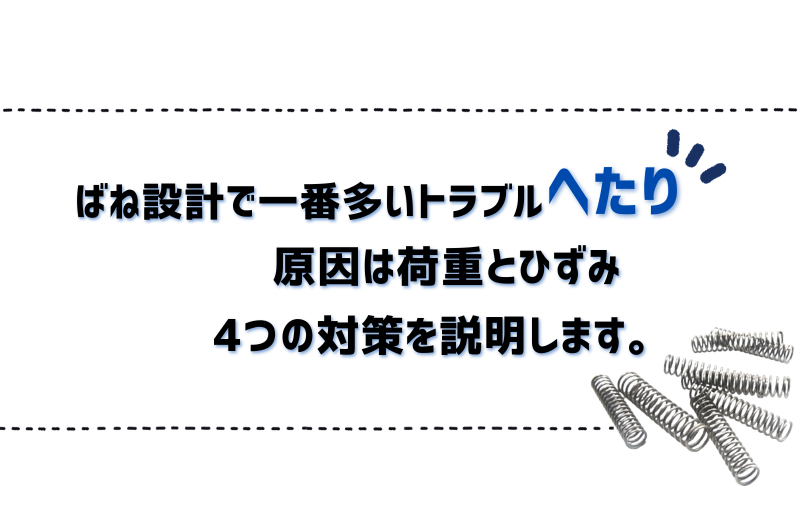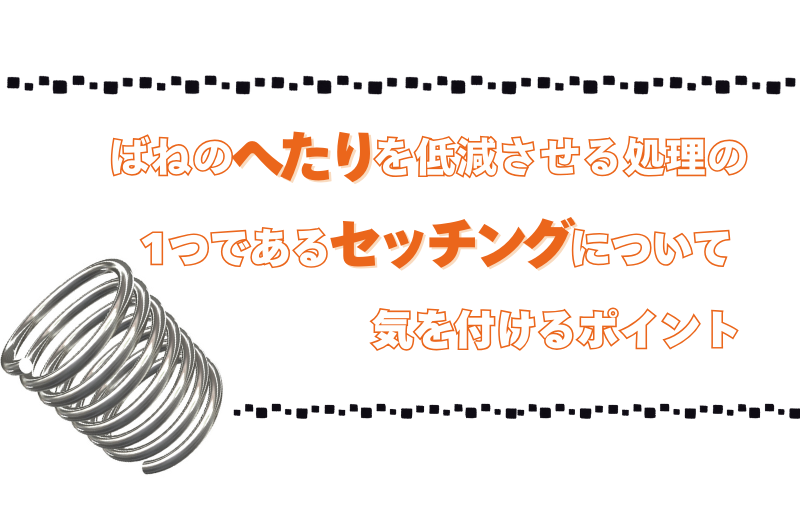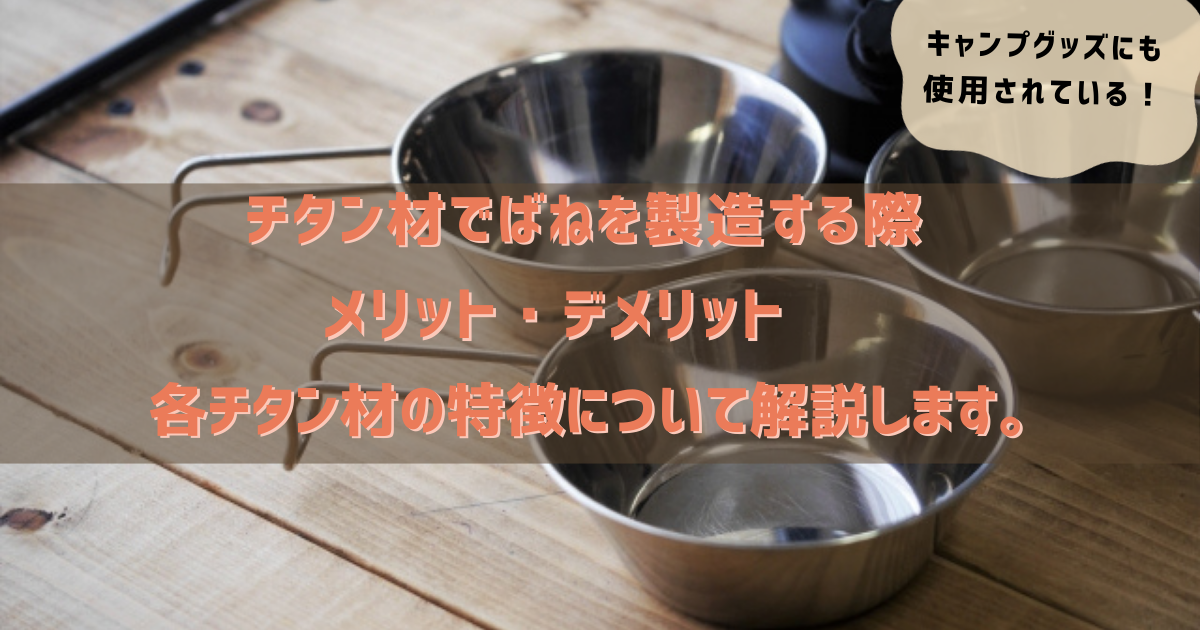ばねのへたりは、最も多く発生するトラブルのひとつです。長期的な使用や高荷重・高温環境下で、バネ性能が低下していることもあります。今回は、へたりのメカニズムと、へたりを防ぐための4つの設計・製造上のポイントをわかりやすく解説します。
ばねのへたりとは
ばねのへたりとは、ばねに荷重を長時間加えた結果、元の寸法に戻らなくなる永久変形のことを指します。
初期は弾性変形(元に戻る変形)ですが、限界を超えると塑性変形(戻らない変形)へ移行し、へたりが発生します。
ばねのへたりが起こる原因
ばねのへたりが起こる原因は主に2つあります
1.設計応力が高すぎる
設計段階で許容応力ギリギリ、あるいは超えていると、使用初期からへたりが進行します。
特に繰り返し荷重が加わる設計では、使用応力を材料の耐久限界の70%以下に抑えるのが目安です。
2.高温環境での使用
高温下では金属の耐力が低下します。これにより、同じ荷重でも塑性変形が進みやすくなり、へたりの原因になります。
特にステンレス系・銅合金系のばねは温度依存性が大きく、高温使用では材質選定や設計応力の調整が必要です。
ばねのへたりを防ぐ4つのポイント
ばねのへたりを低減する対策は大きく分けて4つになります。ポイントもふまえて紹介します。
•材料の機械的性質を安定化(低温焼きなまし)
ピアノ線やステンレスばね材は、加工後に内部ひずみを抱えたままになっています。
200~300℃の低温焼きなましを行うことで、へたりに強い金属組織を安定させることができます。
焼きなまし処理について詳細はこちらをご覧ください。
•残留応力の除去(ショットピーニングなど)
加工後のばねには残留応力が残っています。これが早期のへたりを引き起こす要因に。
ショットピーニング処理や再加熱による応力除去で、内部応力を軽減できます。
•セッチング(初期へたりの除去)
押しバネなどに使用されるセッチング処理では、使用前に設計荷重以上の力を加えることで、
使用中に起こるへたりを事前に取り除くことが可能です。
•材料を高強度材に切り替える
一般的なばね用ピアノ線では限界がある場合、合金鋼系や耐熱ばね鋼などの
高強度材料に切り替えることで、へたり対策につながります。
(参考文献:ばね 入門 日本ばね学会 日刊工業新聞社
ばね 基礎のきそ 蒲久男 日刊工業新聞社)
栄光技研株式会社では、新規ばね設計だけでなく、既存のばねに関するご相談や試作対応も行っております。製品使用環境に応じた提案が可能です。主にばねのへたり対策として低温焼きなましを行っています。ばねのへたりや変形でお困りの方はお気軽にお問合せフォームからお問合せください。
お問い合わせフォームはこちら